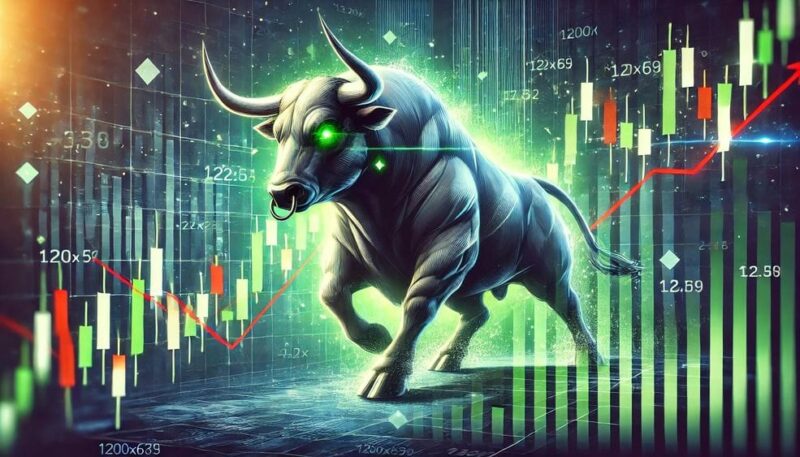こんにちは。Kyleです。
本日は4月7日週の米国株式市場の振り返りです。今週は最も注目されたのはアメリカ長期金利の暴騰と、Reciprocal Tariffs(相互関税)の90日間適用延長でした。今週1週間を通じて歴史的大暴落・急騰が巻き起こり、市場は非常にボラティリティ高い状況が続きました。その他はCPIやPPIなど物価に関する重要経済指標も発表されました。
それでは今週の経済イベントや相場動向を振り返っていきましょう。
今週の経済・政治・金融イベントの総括
4/7〜4/11までの経済イベントと市場の反応は以下の通りです。
- 4/7
- 特に経済指標などはなかったものの、先週発表された相互関税で歴史的な急落を見せた後のリバウンド狙いと思われる買いが入り反転したものと推測します。しかし上髭・下髭ともに長い日足を見せ、市場にも迷いが見えたような気がします。
- 加えて、米国の長期債権金利上昇が大きくなりました(このあたりから米国長期債の売りが始まったと考えられます)
- 4/8
- リバウンドの勢い続くかと思いきや、やはり市場の不透明感を受けてか、SP500も再び大きく下落しました。
- 4/9:FOMC議事要旨
- トランプの相互関税適用の90日延期アナウンスにより市場が歴史的な大暴騰を見せました。
- アナリストたちの分析や後々の報道によれば、日本や中国による米国債権の売りが大きく進み長期金利を急上昇させたことが原因と言われています。これにより、トランプ大統領が今懸念しているのは長期金利の上昇だと明確になりました。
- 4/10:CPI
- CPIは総合もコアも市場予想を下回りました。ただし、前日の歴史的大暴騰により影響が薄い模様です。
- 前日の上昇分を全て帳消しにする勢いで下がりました。前日の上昇が、これまで溜め込んだ買いの勢いの噴出ではなく、ショート勢が焼かれながらのショートスクイーズによるものだったという指摘は新たな学びでした。
- 4/11:PPI、ミシガン大学消費者景況感指数
- PPIは対前月・対前年ともに大幅減少。相互関税による値上げ予想はあったが景気不透明さ、および関税のインパクトが強すぎて各経済指標の影響が弱かった印象
- ミシガン消費者指数も市場予想より下落。消費が弱まっていることに加え、5年先インフレ期待が4.4%になり、インフレ懸念はますます強くなる。

ちなみにこのチャートはTradingViewを使って作成しています。とにかく使いやすくて、毎日の市場チェックに欠かせません。イベントカレンダーやヒートマップなど機能も多彩でおすすめです。
まだ利用されたことのない方は、下記の紹介リンクからぜひご覧ください。
市場の地合いと予想シナリオ
正直、今まで経験したことのないジェットコースターの1週間を過ごし、自身の中で消化できていないことがたくさんあります。ただし、90日の相互関税延長は、1つの大きな転換点になった可能性はあります。
思考の整理も兼ねて、なぜ市場の大きな転換点になったか個々の要素を書き連ねていきます。
長期金利がアキレス腱
4月9日に90日の関税適用延長のアナウンスになった背景であり、世界が今のアメリカのアキレス腱を知った瞬間ではないかと思います。
以前の記事にも記載していますが、7兆ドルという巨額の利払いまたは借り換えを迫られている政府にとっては、なんとしても借り換えの前に金利を下げたいという思惑があると考えます。
しかし反対に、米国経済や政策に不透明感・不安を感じた市場参加者や他の国が米国債権の売却を行い、金利が大きく上昇を見せました。10年金利は最大4.5%に達し、政府がいわば緊急的に90日延長のアナウンスを出して急騰を抑え込もうとしたように思います。

その結果、一旦市場は安堵とともに歴史的なリバウンド高を記録しました。しかしその翌日にはまた大きく下がり、1週間のうちに歴史的に見ても上位の上げ幅・下げ幅を見せました。
株価の歴史的乱高下は一旦落ち着いたように見えていますが、10年金利は4.5%近辺に留まっていて、今後の動きに政府も市場も注目している指標だと思います。
各国との関税交渉
90日間の延長により交渉時間は確保できたため、多くの国と関税交渉がスタートします。
基本的にアメリカに対して強い交渉姿勢を見せれるのは中国、次いでEUくらいだと思います。よってそれ以外の国については、アメリカ政府が気に入るディールを提案できればベースの10%関税以上のものは出てこないように思います。
中国はアメリカに対して125%の報復関税を発動させます。EUは90日間延長のアナウンス後、アメリカへの追加関税の発動を停止させています。
中国は世界2位のアメリカ国債の保有国であり、アメリカのアキレス腱を知れたことにより、今後の交渉カードとして使ってくる可能性が大いにあります。アメリカも中国に対しては強気姿勢を容易には崩さないと考えられ、長期化すればインフレ悪化・景気悪化を促す可能性が高いです。
日本は最大の米国債保有国ですが、交渉カードに米国債売却を使えるものの、同盟国として立ち位置は崩さないでしょうから、やはり焦点は中国との交渉になるだろうと考えます。
なお、4月12日時点ではスマホ、PC、半導体装置の関税を適用除外する考えがトランプ大統領からSNSでポストされたものの、別の政府高官は「続く半導体関連への関税とは別物」というニュースが流れ、どういう方向性になるか4月14日までまた市場は不透明感に揺れることになりそうです。
2025年第一四半期決算シーズン
90日間の関税適用延長により一旦落ち着きを取り戻したことにより、次は2025年第一四半期決算のシーズンに市場は以降すると思われます。
トップバッターであるメガバンク関連はいずれも好調な結果を受け株価は上昇しました。4月14日週の注目はTSMCでしょう。3月受注結果は対前年成長率も順調に伸びており、生成AI相場の一服感が囁かれる市況をさらにブーストできるか、TSMCの結果に期待がかかるところです。
NVDAへの懸念だった中国への半導体輸出規制は、H20が規制適用除外を受けて不安は多少なりとも市場から払拭されているように思います。
とはいえ、政府が4月14日までに個別商品カテゴリごと関税に関するアップデートをアナウンスする予定であることから、ボラティリティ高い相場は継続するでしょう。
今週の学び
相場で生き残る「逃げ足の速さ」
今週の乱高下によって相場退場を余儀なくされた人がいるというコメントをX(旧Twitter)でも見ました。同感です。
自分は2月の時点で利確・損切りをしてキャッシュ比率90%くらいだったので被弾は抑えられていると思いますが、そうであっても長期投資枠だったETFは過去1年間の投資が無かったことになるくらい減りました。
長期投資なのか、短期トレードなのかで考え方や投資手法は変わるものの、何はともあれ、最も大切なスキルの一つは「逃げ足の速さ」だと思います。
違和感を抱き怪しさが拭いきれない場合は「長期投資だから」と意地張るよりかは、まずは逃げて相場に居残り続けられることを優先しても良いのではないかと考えました。
ちょうどTaxシーズンなのもあり、短期売買による税金支払いのインパクトはしっかり学ばされましたが、同時に、時には柔軟に逃げ足の速さを意識することも大事なスキルだなと感じました。
まとめ
- 相互関税の90日間適用延長により相場はさらに大転換
- 債権市場の動きにも要注目
以上です。ご覧いただきありがとうございました。